株式会社いのまとぺは、子ども向けの日本語教育プログラムの開発・販売と、地域資源を活用した体験型イベントの企画・運営を軸に、教育と地域、そして人の可能性をつなぐ事業を展開しています。
今回取材した井上さんは、以前はエスイノベーション株式会社のメンバーとして、オープンイノベーションや地域連携の現場に深く関わってきた人物です。niigatabaseでも過去に取材を行い、「今」と向き合いながら挑戦を重ねる姿を紹介してきました。
その井上さんが、これまでの経験や原体験をもとに立ち上げたのが、今回紹介する株式会社いのまとぺです。
テーマに据えたのは、日本に暮らす外国にルーツを持つ児童生徒を取り巻く「日本語教育」という課題、そして地域と人をつなぐ「体験」の価値でした。
なぜこのテーマなのか。
なぜ今、事業として取り組むのか。
今回は、井上さん自身の原体験を起点に、現在のアクションへとつながる思考の変遷と、向き合おうとしている社会課題の輪郭を紐解いていきます。
井上 佳純さん Inoue Kasumi
1992年生まれ、新潟市秋葉区出身。県内高校を卒業後、大学に進学で関東へ。小売業、学童保育指導員、日本語教師、地域おこし協力隊、NPO職員、そして新潟のスタートアップ企業にてオープンイノベーション事業を担当。県内大手企業とスタートアップの事業共創の推進に取り組み、2025年末に独立。自らのテーマであった、教育領域での継続的な事業化に挑むべく〈株式会社いのまとぺ〉を創業。現在は事業構想の実現に向けて奔走中!
ルーツを繋ぎ合わせた、その先にあったもの
ーーまず、井上さんが「株式会社いのまとぺ」で挑もうとしていることは何でしょうか。
井上 佳純さん:大きく言うと、二つの軸があります。
一つは、日本語の支援が必要な子どもたちに向けた、日本語教育プログラムの開発と提供です。小学生から高校生を対象に、日本の学校生活の中で困りごとを抱えやすい外国にルーツを持つ児童生徒に向けて、学びを支える仕組みをつくろうとしています。
もう一つは、地域資源を活用した体験型のイベントづくりです。こちらは、教育と観光の要素を半分ずつ持ったような取り組みで、親子や家族を対象に、地域の文化や自然、人と触れ合う体験を通じて学びを深めていくものです。
どちらにも共通しているのは、「知識として教える」だけではなくて、実際の体験や日常と結びついた学びを届けたい、という思いです。
日本語教育も、地域体験も、最終的には「ここで暮らす」「ここで生きていく」という実感につながっていくものだと思っています。
ーーその二つを、事業として取り組もうと思った最初のきっかけは何でしたか。
井上 佳純さん:一番最初のきっかけは、2017〜2018年にベトナムで日本語教師をしていた経験です。
当時は、「日本語教育をやりたい」という意思があったわけではなく、「海外で働いてみたい」という気持ちから仕事を探していたんです。いろんな選択肢がある中で、自分ができることを整理すると「日本語教師」という仕事が一番しっくりきたので、飛び込んでみることにしました。
ーー実際にベトナムで日本語教師をやってみて、どんなことを感じましたか。
井上 佳純さん:日本で生まれ育って、日本語を話すこと自体は当たり前にできる。でも、”言語”としての日本語を教えようとした時、想像の何倍も難しくて、全然うまく教えられなかったんです。文章の成り立ちや、仕組み、そこに付随してくる由来など、何一つ分かっていなかったことに気づきました。
それがすごく虚しくて、改めて言語として日本語と向き合うようになりました。結果的に、その1年が人生で一番、日本語を勉強した時間だったと思います。
日本語センターで教えていた学生たちは、「日本に行きたい」「日本で学びたい」「日本で働きたい」という強い意欲を持っていました。その熱量が本当に高くて、「この人たちの思いに応えたい」と思うほど、自分も必死に勉強せざるを得なかった。
外国語として日本語を見ることで、日本語の面白さや、日本文化の奥行きにも気づけました。外国に行ったはずなのに、日本のことを深く知って帰ってきた。そんな感覚でした。

「自分の意思で来たわけではない」子どもたちと向き合って
ーーその経験は、今の事業とどうつながっているのでしょうか。
井上 佳純さん:当時ベトナムで教えていたのは、「日本に行きたい」と自分で決めて、日本語を学んでいる学生たちでした。
でも今、向き合っているのは、そうではない子どもたちです。
日本に来ている外国にルーツを持つ児童生徒の多くは、親が先に日本で働いて、生活が安定したから呼ばれている。
留学ではないので、「学びたい」「日本に来たい」という明確で自発的なモチベーションが最初からあるわけではありません。
それでも、日本の公立学校に通い、日本語で授業を受ける。
その環境の厳しさを、実際の現場で目の当たりにしました。
ーー実際、どんな場面に「違和感」を感じましたか。
井上 佳純さん:特に中学生や高校生になってから来日する子どもたちを見ていて、違和感を強く感じました。
周囲の同級生は、すでに母語として言語が完成した状態で、各教科を学んでいる。でも彼らは、日本語が分からない状態で、すべて日本語で授業を受けることになる。学校の先生が英語や彼らの母語でフォローできるわけでもない。
学校で交わされている情報が分からない。友達とも十分にコミュニケーションが取れない。
これでは家に帰っても、学校で何があったのかを親に説明できない。
それでも時間は進んで、学年は上がり、定期テストや受験はどんどんやってくる。
そんな状況の中で、彼らは本当に必死に、毎日学校の宿題をして日本語の勉強もしている。
その姿を見て、「あまりにも個人の努力に委ねられすぎている」と強く感じました。
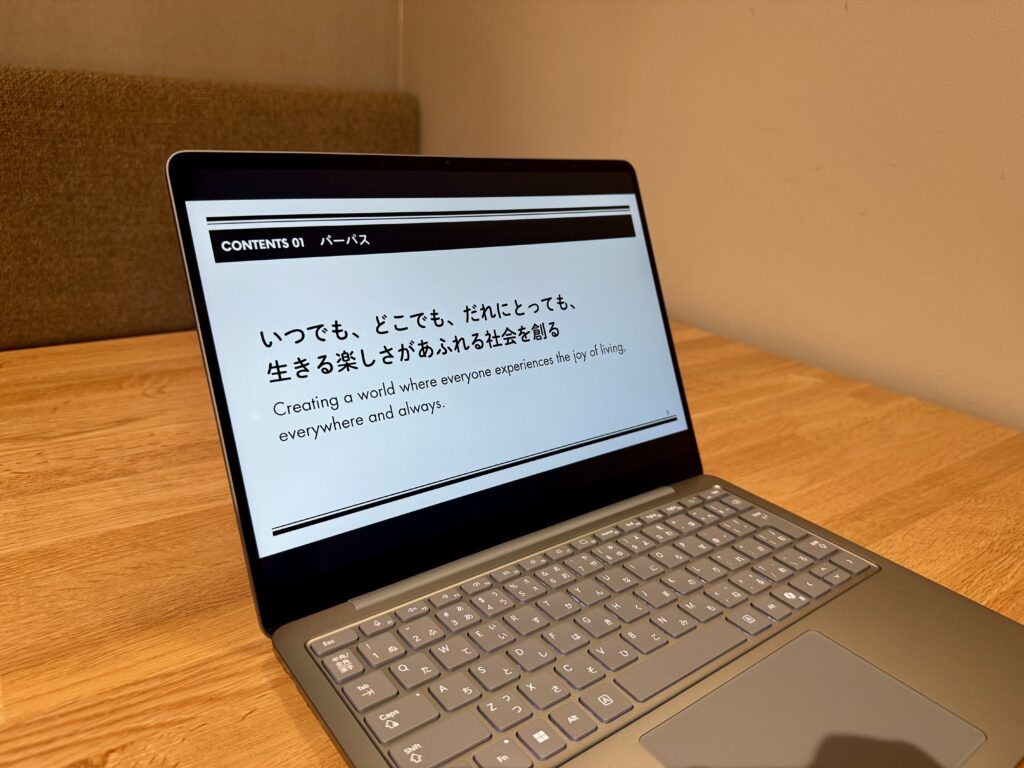
このままではいけない、という感覚が消えなかった理由
ーーいま、「株式会社いのまとぺ」で井上さんがその違和感に挑みたいこととは?
井上 佳純さん:まず、一番避けたいのは、「あの時、日本に来たから教育を受けられなかった」という後悔を残してしまうことです。
日本が嫌いになってしまうとか、可能性を閉じてしまうとか、そういう結果にはしたくない。
たまたま来ることになった日本かもしれないけれど、将来を描きながら、前を向いて過ごしてほしいと思っています。
ベトナムで、日本に希望を持って旅立とうとする学生たちを支援してきたからこそ、日本側の受け皿が不十分で、来日経験そのものがネガティブになってしまうのは、あまりにももったいないと感じるんです。
ーーその課題は、なぜ既存の制度では解決しきれていないのでしょうか。
井上 佳純さん:制度や学校、行政が何もしていないわけではありません。
ただ、「日本語教育」「学校教育」「生活支援」「将来の進路」がどうしても分断されていると感じます。
親御さんも、日本の学校制度を十分に理解できていないケースが多い。学校側も、そこまで踏み込む余裕がないのが現実です。さらに、新潟のような子どもと支援者が点在している「散在地域」では、まとまった継続的な支援を行うのが非常に難しいという現状もあります。全国的に見ても、ボランティアありきの支援体制が多いです。
結果として、支援が点在してしまい、子ども本人が“全部一人で頑張る”構造になっている。そこに、強い違和感がありますね。

ーーこの課題を、なぜ「いま」事業(ビジネス)として取り組もうと思ったのでしょうか。
井上 佳純さん:まず、この課題を放置してしまうと、子どもたちの教育でのつまずきが、そのまま進学や就職につながってしまうという現実があります。一人ひとりの問題として見られがちですが、実は社会全体に影響していく話だと考えています。
十分な教育や支援が届かないまま成長してしまえば、本人にとっても、社会にとっても大きな損失になる。
逆に言えば、ここにきちんと向き合い、投資していくことができれば、未来は大きく変えられるはずだと感じています。
そしてもう一つは、タイミングです。
現在、外国人労働者やその家族は増えていますし、日本語教員の国家資格化など、制度面でも少しずつ変化が起き始めています。
ようやくこの領域に光が当たり始めた一方で、まだ拾いきれていない部分が多い。
だからこそ今、現場の声を起点にした取り組みを、継続できる形でつくっていく必要があると思いました。
この課題は、決してニッチではありません。向き合い方次第で、教育にとどまらず、地域や社会全体に広がっていくテーマだと考えています。
ーー前職では、オープンイノベーションの現場で多くの企業やプロジェクトに関わってきたと思います。そうした経験を経て、今回は自身が起業をして挑戦しようと決めたのは、なぜだったのでしょうか。
井上 佳純さん:前職では、本当にいろいろな企業の方とプロジェクトを進めてきました。その中で、企業が持つ事業のスピード感や推進力を目の当たりにするシーンが多くありました。
一方で、教育や福祉の分野はどうしてもクローズドになりやすく、ビジネスとして広がりきらない構造も見てきました。
オープンイノベーションの現場で、領域の違う人たちが目的を共有して動くことで価値が生まれていく様子を見て、「このやり方は教育の領域でも生かせるかもしれない」と思うようになりました。
まだ事業の構想も仮説の段階で、これから実証していくフェーズではありますが、企業や地域がそれぞれの強みを持ち寄って社会課題に向き合う、その先陣役として挑戦していきたいと思っています。
***
井上さんの話を聞いていると、「社会課題」という言葉が、決して遠いものではないことに気づかされます。
それは、たまたま日本に来た子どもたちの、今日の授業であり、明日のテストであり、数年後の進路の話です。
一人ひとりの時間を、失われたままにしないために。
その思いが、井上さんの現在のアクションにつながっています。
次回は、この課題に対してどのようにビジネスとして向き合っているのか、その具体像に迫ります。






